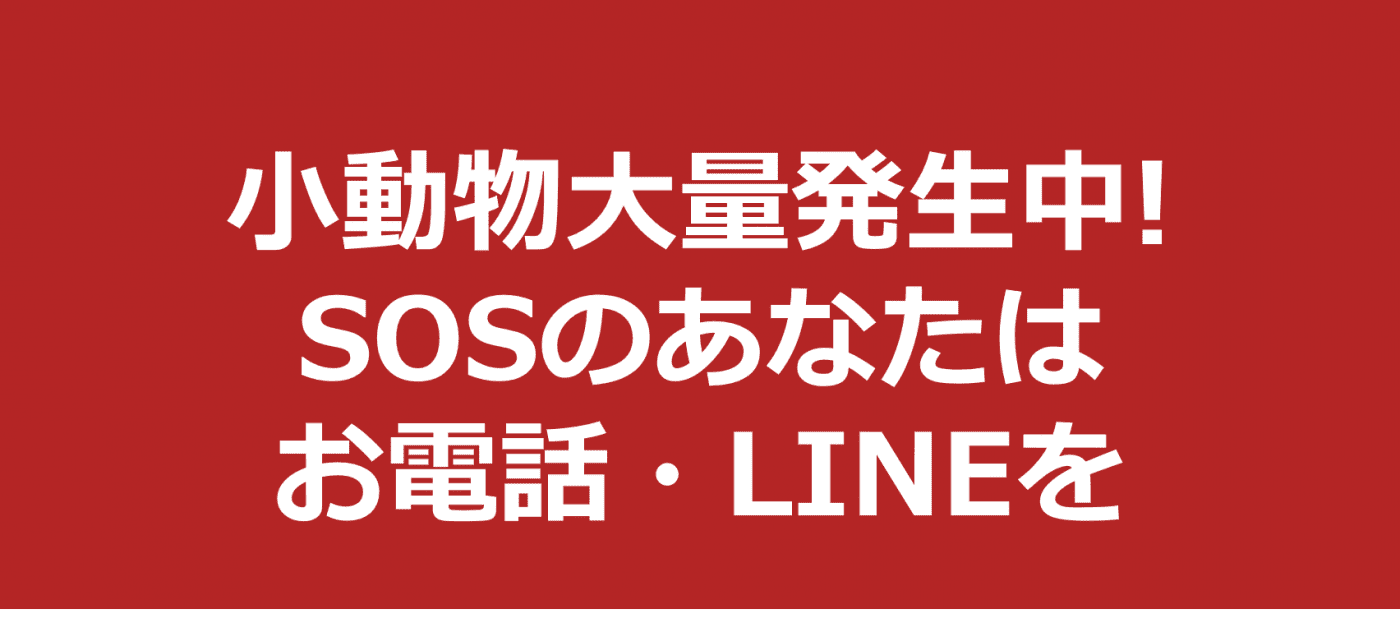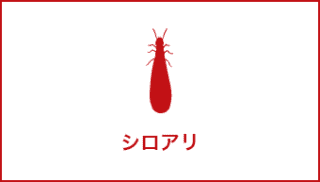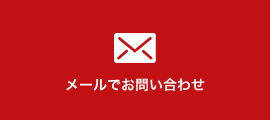春のシーズン商品
NEWS
| RSS(別ウィンドウで開きます) | もっと見る |
GENERAL SERVICE
一般サービス一覧
一般サービス一覧
CORPORATION
法人のお客様へ
法人のお客様へ
宿泊施設・病院・介護施設
文化財・古民家・書籍
サービスの流れ
SERVICE FLOW
SERVICE FLOW
1 | お問い合わせ | お電話、メール、お問い合わせフォーム、Instagram、LINEからまずはお気軽にご連絡ください。 |
2 | 現地調査 | 被害状況調査、生息調査を致します。 |
3 | お見積り | お客様のご希望に沿ってご提案致します。 |
4 | 初回施工 | 当社取扱いの様々なトラップで各種害虫・害獣の駆除対策を施します。 |
5 | 定期訪問 | 効果的なスパンで施工を継続し、モニタリングにて環境診断をしていきます。 |
6 | 原状復帰・再発防止策 | ご要望に応じて清掃・消毒・侵入口の封鎖など承ります(別途見積り) |
7 | 報告書提出 | 駆除予防が完了しましたら報告書を作成し、今後の対策もアドバイス致します。 |
| 8 | ご請求 | お振込みか現金でお支払いください。 |